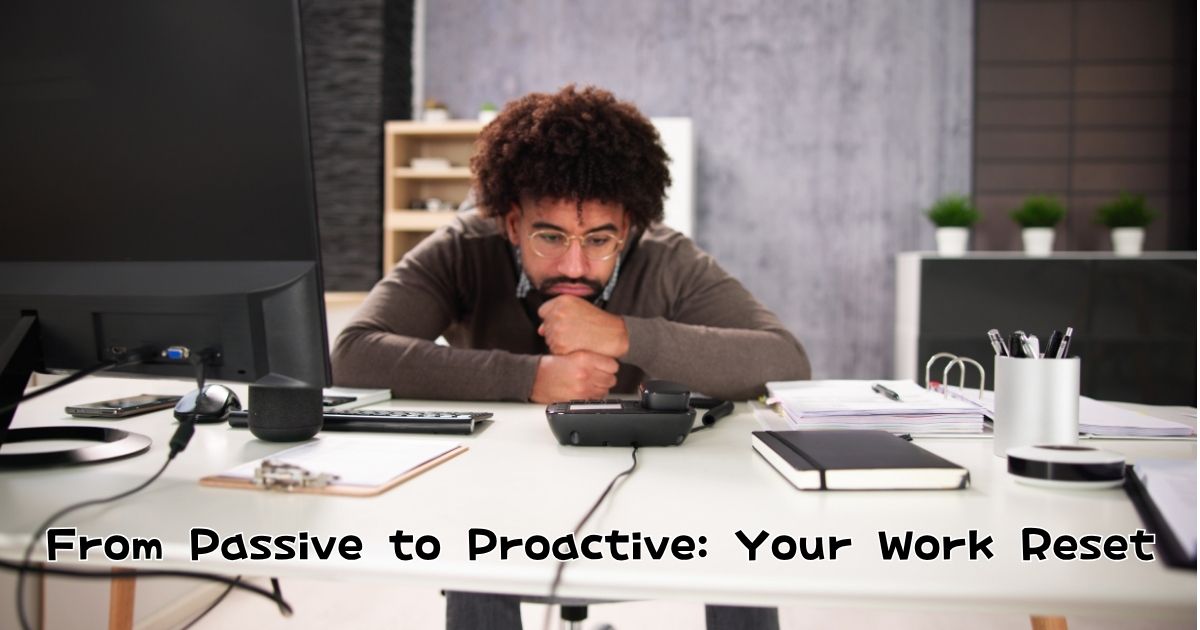「また指示を待ってる……」「結局、自分で考えて動かない……」 職場でそんな場面に直面し、モヤモヤしたことはありませんか?
それが他人であれ、自分であれ、「受け身な働き方」には誰もが一度は悩まされます。
やる気がないのか?能力の問題なのか?それとも環境が悪いのか?
実は、受け身になる背景には「性格」だけでは語れない、思考のクセや職場文化、信頼関係など、複雑な要因が絡んでいます。
この記事では、自分が受け身から抜け出したい人、部下や同僚の受け身さに悩む人、組織として改善したい人に向けて、 「なぜ人は受け身になるのか?」という根本から、「どうすれば主体的に働けるか?」という具体策までを解説します。
あなた自身も、あなたの周囲も、一歩前に進むヒントが見つかるはずです。
- 人が受け身になる心理的・環境的な原因
- 自分が受け身から抜け出すための具体的ステップ
- 部下や同僚が受け身なときの関わり方・導き方
- 受け身を助長する職場文化や組織構造の正体
- 主体性を育むために実践したい習慣や対話のヒント
受け身とは何か?「指示待ち」の裏にある心理構造

あなたの周りに、こんな人はいませんか?
- 指示がないと動かない
- 自分の意見をほとんど言わない
- トラブルが起きても距離を置く
あるいは、自分自身に思い当たる節があるかもしれません。
でも──それって本当に「やる気がない」からでしょうか?
実は、受け身な姿勢の裏には、次のような『心のブレーキ』が隠れています
- 責任を取りたくない(叱られるのが怖い)
- 失敗が怖い(完璧主義や過去の経験)
- 嫌われたくない(人間関係の摩擦を避けたい)
たとえば、こんなふうに考えてしまうこと、ありませんか?
「これ、自分で動いたら逆に迷惑かも…」 「黙ってた方が無難だよな…」
これは、『自信がない』というより、『傷つきたくない』という感情が強く働いている状態です。
さらに重要なのは、文化的な背景です。
日本の職場では、「出しゃばらない」「空気を読む」「上司の判断を仰ぐ」といった態度が評価されがち。
つまり──
「意見がない」のではなく、「出すのが怖い」
そんな“控えめ”な行動が、結果として受け身を助長していることも多いのです。
この前提を知ることが、「どうすれば主体的に動けるのか?」を考える出発点になります。
【自分編】なぜ私は受け身なのか?その原因と向き合うヒント

自分が「受け身になっているな…」と感じたとき、自己嫌悪や焦りが先に来てしまう人も多いかもしれません。
でも、まず大切なのは「責める」のではなく「知る」ことです。
実際、多くの人が受け身になるきっかけには、こんな背景があります:
- 過去に「出しゃばって」失敗した経験がある
- 自信のなさから「どうせ自分なんて」と思ってしまう
- 「考えるより従った方が早い」と習慣化している
- 自分の提案が軽く扱われた、否定されたことがある
こうした経験が積み重なると、「前に出るのは危ない」「指示を待つ方が安全」といった思考パターンができあがってしまいます。
つまり、受け身は「思考のクセ」であり、習慣の結果。
だからこそ、少しずつ意識を変えていくことで修正は可能です。
次章では、その第一歩として「どうすれば自分の受け身を直せるか?」を具体的に見ていきましょう。
【自分編】受け身から抜け出すには?小さな習慣と考え方の変え方

受け身の状態から抜け出すには、「いきなり主体性を持て!」ではうまくいきません。
まずは「考え方」と「行動」の両面から、小さなステップを積み重ねることが大切です。
1. 「確認」より「提案」を心がける
つい、「これで合ってますか?」と確認したくなりますが、そこをあえて、
「○○だと思いますが、いかがでしょうか?」
と提案型の言い方に変えるだけでも、相手の受け止め方が変わり、主体的な印象を与えられます。
2. 小さな「自分判断」を毎日つくる
・昼ご飯を何にするかを他人に合わせず決める
・ToDoリストを自分で整理してみる
・上司に言われる前に「これ確認しておきました」と報告する
こうした「自分で選ぶ」機会を意識的に増やすことで、判断するクセが身につきます。
3. 失敗への『構え』を持つ
「失敗しないように」ではなく、「失敗した時どうするか?」を先に考えておくと、 過度な不安が減り、動けるようになります。
- 事前にリカバリープランを用意する
- 上司に「もしこうなったらどうしましょう?」と相談しておく
など、「逃げ道のあるチャレンジ」は、主体性の訓練に有効です。
これらを少しずつ試していくだけで、 「なんとなく受け身だった自分」が、 「少しずつ動ける自分」へと変わっていきます。
【他人編】受け身な部下・同僚にイライラするときの視点転換と関わり方

「なんで指示しないと動かないの?」「もっと考えて行動してよ…」
受け身な同僚や部下を見て、そう思ったことはありませんか?
しかし、ただ叱ったり「もっと自分で動いて」と言うだけでは、 その人の行動が劇的に変わることはほとんどありません。
なぜなら、受け身な行動の背景には「心理的な壁」や「過去の経験」があるからです。
1. 「なぜ動けないのか?」を聞いてみる
失敗したくない気持ちが強いのか? 正解を求めすぎているのか? 判断基準が不明確なのか?
まずは「なぜ?」に寄り添う対話を重ねることで、相手のブレーキを理解できます。
2. 指示より「意図」を伝える
「この作業、こういう理由で重要なんだ」
背景や目的を共有することで、相手が“考える余白”を持ちやすくなります。
「何をするか」だけでなく、「なぜやるのか」を伝える習慣は、 受け身から主体性へのスイッチを入れるカギになります。
3. 小さな成功体験を積ませる
いきなり大きな判断を任せるのではなく、 「この部分だけ任せるね」と、成功しやすい範囲を少しずつ広げていきましょう。
成功の積み重ねが、「やっていいんだ」「信頼されている」という自信につながります。
他人の受け身を変えるには、強制や正論ではなく「信頼」と「対話」が重要です。
相手を責める前に、「どうすれば動きやすくなるか?」という視点に立つことで、 関係性も職場全体の空気も、じわじわと変わっていきます。
【職場編】受け身を生む組織・文化とその改善策

個人やチームの受け身体質は、実は「職場環境」によってつくられていることも少なくありません。
いくら個人が努力しても、組織全体が「待ち」「静観」「トップダウン」では、主体性が育ちにくいのです。
では、受け身を生む職場とはどんな特徴を持っているのでしょうか?
1. 指示・承認がすべて「上司待ち」
- 自由な判断が認められていない
- ミスを恐れる文化が根づいている
- 「とりあえず上司に確認」が暗黙のルール
このような構造では、誰もが「指示待ち」になります。
2. フィードバックが乏しい・一方通行
- 成果に対してリアクションがない
- 改善点だけ伝えて「よかった点」は無視
双方向のコミュニケーションがない職場では、自分から意見を出す動機も生まれにくくなります。
3. 「変化を嫌う」空気がある
「前例がない」「うちはこうだから」など、新しい提案や工夫が歓迎されない文化も、 受け身を助長する大きな要因です。
これらを改善するには、組織として「信頼」と「裁量」を育む土壌をつくることが鍵です。
- 判断を任せる範囲を明確に伝える
- 挑戦したことを評価する仕組みを整える
- 小さな意見交換の場(1on1や朝会など)を増やす
職場文化はすぐには変わりませんが、小さな「開かれた対話」の積み重ねが、 受け身から前向きな動きへの転換点となります。
まとめ 受け身な職場から「前に進む」職場へ

受け身であることは、決して悪ではありません。 そこには「傷つきたくない」「信頼されたい」「安心したい」といった、誰もが持つ人間らしい気持ちが潜んでいます。
でもそのまま放っておくと 個人の成長も、チームの力も、止まったままになってしまう。
だからこそ、
- 自分の思考のクセに気づき
- 小さな選択から「動ける自分」を育て
- 周囲にも「動ける空気」を広げていく
そんな一歩を、今日から踏み出してみてください。
主体性は、生まれ持った才能ではなく、「育てるもの」。
自分の中の受け身と向き合い、周りと対話を重ねることで、 あなたの仕事も、チームも、少しずつ変わっていくはずです。