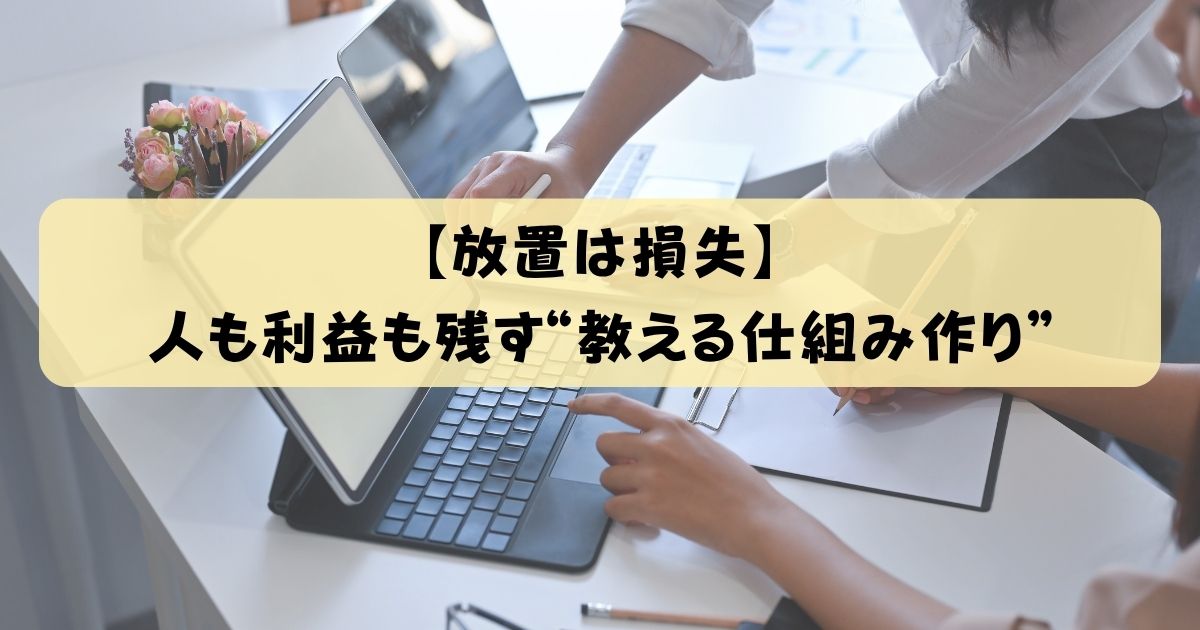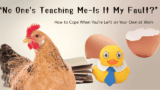「最近の若手は自分で考えようとしない」
「教えても、すぐ辞めてしまう」
「指導に時間を割く余裕がない」
もしあなたの職場でこうした声が聞かれるなら、それは“人が育たない組織のサイン”かもしれません。
実は、新人や若手が辞めていく背景には、「教えない文化」や「育成の仕組みの不在」が隠れているかもしれません。
忙しさの中で指導を後回しにしてしまうことは、短期的には楽でも、長期的には人材も利益も失うリスクにつながります。
一方で、きちんと“教える仕組み”が整っている職場では、人も育ち、定着し、生産性も上がります。
育成はコストではなく“投資”です。
この記事では、職場における「教える仕組み作り」の具体的ステップと、上司や組織側がすぐに実践できる行動を紹介します。
人も利益も残すために、いま何を整えるべきかを一緒に考えていきましょう。
・新人がすぐ辞めてしまう職場の共通点
・教える文化と仕組みが“利益”に直結する理由
・現場ですぐ始められる育成設計の方法
・上司・会社側が改善できる具体アクション
・新人側に問題があるときの適切な見極め方
新人が辞める職場の3つの構造的問題

新人が早期に辞めてしまう職場には、いくつか共通する“構造的な問題”があります。
ただの相性や根性論ではなく、「教えない仕組み」そのものが、無意識に組織に根づいているケースがほとんどです。
① 教える側が“忙しすぎて”余裕がない
教育担当や中堅社員が、本来の業務に追われて「教える時間」がとれない状態。
結果的に、新人にかけるはずの時間が削られ、「自分で覚えて」と突き放す形に。
🗣️現場の声:「マニュアルもあるし、聞かれたら答えてる。こっちも余裕ないんだよね…」
➡ 教育が属人的になり、引き継ぎのたびに“人によって教え方が違う”という不満も生まれる。
② 「育成=非効率」と見なす文化
「即戦力でなければ意味がない」「教える時間はコストでしかない」という思い込みがある職場では、新人育成の価値がそもそも理解されていません。
🗣️上層部の声:「今は余裕がないから、新人は空気読んで動いてくれないと…」
➡ こうした空気が、“教えてもらえないのが当たり前”という誤った常識を生み、次第に定着していきます。
③ 「できて当たり前」と思い込んでしまう
指導側が「自分も誰にも教わらずに覚えた」という経験を持っていると、新人にも“自然にやって当然”という過剰な期待を持ってしまいがちです。
🗣️よくある勘違い:「やる気があれば、自分で聞くでしょ」「質問されない=わかってる」
➡ 実際は「何を聞いていいかもわからない」状態なのに、黙っていることが“理解している”と誤解されてしまいます。
教える仕組み作りが利益につながる理由

「教育」は時間と労力を消費する、ただのコストのように思えるかもしれません。
しかし、実際は教える仕組みが職場の利益や生産性に直結します。
1. 離職コストが減る
新人の早期離職には、採用コスト、引き継ぎロス、再教育コストなどが伴います。
教える仕組みがないことで、これらの損失が繰り返されていくのです。
💸新卒一人の早期離職で失われるコスト:約100万円以上(採用〜配属までにかかった総コスト)
2. 定着率が上がることで、チームの生産性が向上
同じメンバーが長く働くことで、チームのコミュニケーションはスムーズになり、業務効率も高まります。
新人が安心して学べる環境は、自然とチームの雰囲気も良くなります。
📈「教えてもらえる環境」=心理的安全性がある職場=提案や改善が活発になる
3.教える側の成長も促される
教えることは、業務を言語化・体系化する機会です。
中堅層が「なぜそうするのか」を伝える過程で、視野や論理的思考が鍛えられ、結果的にマネジメント力も伸びていきます。
🎯教えるスキルは、マネージャー・リーダー層に必須の資質
4. 組織全体の“共通認識”が強化される
「このやり方でOK」「ここでつまずきやすい」といった知識を共有・継承することで、属人化が防がれ、誰でも一定水準で業務ができるようになります。
🧠ベテランの“頭の中”を言語化し、仕組みに落とし込むのが育成の第一歩
人も利益も残す“教える仕組み”7つのステップ

「教える仕組み」とは、個人の「善意」や「時間があるときだけ」に頼るものではなく、組織的に設計・運用される教育の土台です。
以下の7ステップは、実際の企業やチームでも成果が出ている実践法です。
① 新人の“最初の30日設計”をつくる
- どの順番で何を覚え、誰に聞けばよいのかを見える化
- 日別・週別の「習得目安」や「期待役割」を明示する
📝例:「1週目:社内ツールの習熟/2週目:○○業務の流れ習得/3週目:〜」
② 教育担当者の役割と業務を明確にする
- 教育係の「片手間指導」を防ぐため、明示的に時間を割り当てる
- トレーナー経験を評価指標に入れる
📌例:担当者が「教える時間が業務として認められている」と感じられる体制づくり
③ マニュアル+質問OKな文化の整備
- マニュアルを渡して終わりにせず、更新・補足・質疑のプロセスも含める
- 「いつでも質問していい」空気を作る言葉がけも忘れずに
🗣️例:「これ、迷いやすいところだから遠慮せず聞いてね」
④ 業務の“意味”も一緒に伝える
- 「作業のやり方」だけでなく、「なぜそれをするのか」まで共有する
- 意味がわかると、自主性が生まれやすくなる
🎯例:「このチェックを入れるのは、トラブルを未然に防ぐためなんだよ」
⑤ フィードバックの“頻度と質”を上げる
- 定期的に声をかける(最低週1回は「観察+感想」)
- 「できていないこと」ではなく、「できるようになったこと」も積極的に伝える
📣例:「ここ、前よりスムーズになってたよね!」
⑥ 成長記録を“見える形”で残す
- Notionやスプレッドシートなどで進捗を記録・可視化
- どこまで理解しているかを共有することで、上司もサポートしやすくなる
📊例:新人が自己チェックできる「習得チェックリスト」を運用
⑦ 「教える力」を評価制度に反映する
- 教育貢献も業務の一部として正式に評価
- 「新人を成長させた人」が評価される文化へ
🏅例:育成対象の進捗も、育成者の人事考課に加点される仕組み
上司として今すぐできる3つのアクション
制度や体制を整えるのには時間がかかることもありますが、上司自身のちょっとした行動で、新人の安心感ややる気は大きく変わります。
育成に関わる上司自身が、まず自己管理力と主導性を身につけることも欠かせません。
リーダーとしての在り方を整えるヒントはこちらの記事で解説しています。
以下は、今日からすぐにできるアクションです。
1. 「質問しやすさ」を意図的につくる
新人が何も聞いてこないのは、「聞きにくい」と感じているからかもしれません。
質問を引き出すには、まず上司から“聞きやすい空気”を発信しましょう。
💬使えるひとこと例:
- 「自分も最初よくわからなかったよ、聞いて正解」
- 「わからないのは当然。遠慮しないで聞いてね」
- 「これは混乱しやすいところ。どこか気になる?」
2. 進捗を認めるフィードバックを届ける
新人は「合ってるかどうか」がわからないまま、毎日を手探りで過ごしています。
小さな進歩に気づき、声をかけるだけで、彼らの安心感は段違いに変わります。
💬たとえばこんな声かけ:
- 「昨日より早くできてたね、すごい」
- 「そこ、覚えたのすぐわかったよ!」
- 「確認のタイミング、ちょうどよかった!」
3. 忙しいときこそ「確認どう?」と先回りする
上司側が忙しいと、つい新人にかまう時間が後回しになります。
だからこそ、「こちらから声をかける」ことが、信頼づくりの第一歩になります。
📣シンプルだけど効果的な一言:
- 「困ってることない?いま少しなら聞けるよ」
- 「この業務、つまづきやすいから先に確認しとこうか」
このようなアクションを続けることで、新人にとってあなたは「信頼して相談できる存在」になります。
新人に問題があるときの見極め方と対処法
教える環境や仕組みを整えても、うまく機能しないことがあります。
その原因が新人本人の姿勢・性格・態度にある場合も、もちろん否定できません。
ただし、ここで重要なのは、環境のせいか本人の課題かを見極めることです。
新人はこう考えている場合も:
本当に“受け身”なのかを客観的に見直す
新人が「受け身」「自走しない」と見えるとき、
それは“質問できない空気”が原因ではないか、まず確認しましょう。
✅チェックポイント:
- 質問していいタイミングを伝えているか?
- 質問を受けたときの反応が冷たくなっていないか?
- 「気にせず聞いて」と言葉にして伝えているか?
明確な期待値を伝えているかを確認
「これくらいはできて当然」と思っている業務でも、
新人にとっては何が「ゴール」なのか分かっていないことが多々あります。
🎯例:
- 「今日中にこの資料を“〇〇の形”で完成させてね」
- 「わからなければ15分以内に聞いても大丈夫」
➡ あいまいな期待は、行動の遅れと不信感の原因になります。
課題がある場合は“対話”で修正を促す
もし本当に取り組み姿勢や理解力に課題があると感じたら、
評価ではなく「対話」を軸に修正を促しましょう。
🗣️使えるフレーズ:
- 「今の進め方で、どこが難しかった?」
- 「どう進めたらやりやすいと思う?」
- 「ここはこう進めてくれると嬉しい。できそうかな?」
➡ 一方的に“できてない”と突きつけず、本人の視点を引き出すことが鍵です。
まとめ:教える仕組みが人も利益も守る
「新人が辞めるのは根性がないから」
「こちらから教えなくても、自分で学ぶべき」
そうした考えが職場に根づいていると、気づかないうちに人も利益も失っているかもしれません。
放置は、育たないだけでなく、信頼も失わせる“組織的損失”です。
一方で、教える仕組みを整えた職場では──
- 人材が定着し、組織に知識が蓄積される
- 教える側も成長し、チーム力が上がる
- 生産性と心理的安全性が両立する
育成はただのコストではなく、未来への投資です。
「人を育てることは、会社を育てること」
その第一歩は、
「属人的な教え」から、「仕組みある育成」へと進化することです。
🎯 今日からできる一歩を踏み出すことが、未来の離職を減らし、組織を強くします。
現場を知るあなたが、文化を変える行動をとりましょう!